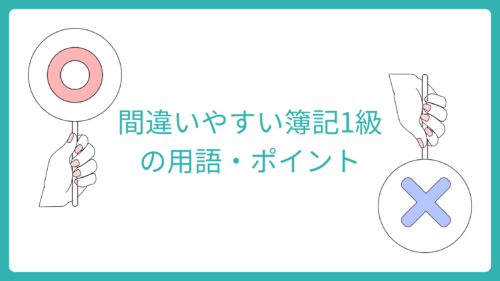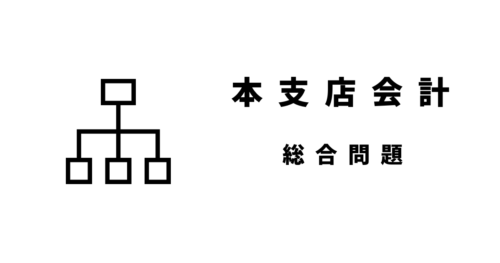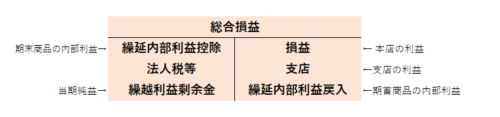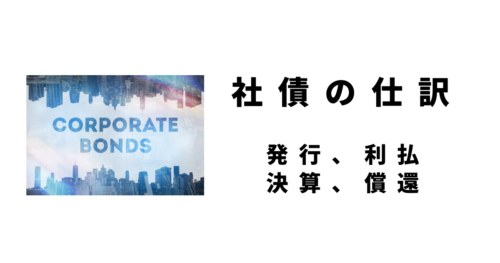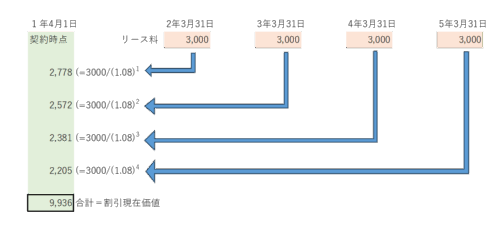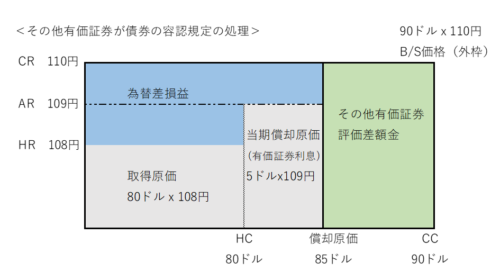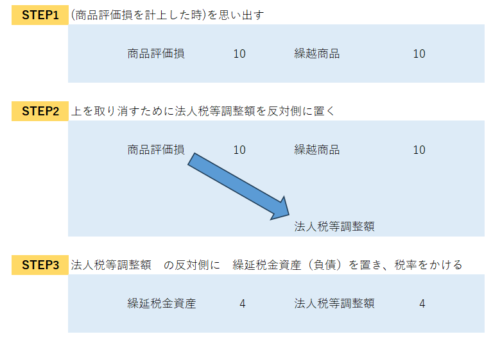私がよく間違えた問題ばかり集めています。備忘録的なものなので参考程度にどうぞ。
使い方は、( )に入る言葉を答えていきます。正解は右の▼を押せば表示されます。
全体編
Q:部門別計算の第2次集計での直接配賦法は、補助部門費の配賦計算上、補助部門間の用役授受を( )に配賦します。それに対し、相互配賦法は、補助部門間の用役授受を( )する方法です。
A:無視し製造部門のみ、すべて考慮
総合原価計算
Q:度外視法と非度外視法の違いは( )の金額を計算するかしないかである。
A:正常減損費
Q:度外視法で、正常減損の発生点 >月末仕掛品の加工進捗度の場合、正常減損費は( )に負担させます。
A:完成品のみ
完成品原価は合計金額から月末仕掛品を引いた差額により計算。(自動的に完成品のみが正常減損費を負担)
Q:度外視法で、正常減損の発生点 <月末仕掛品の加工進捗度の場合、正常減損費は( )に負担させます。
A:完成品と月末仕掛品の両方
完成品原価は、正常減損の数量を省いた形で計算。材料費で先入先出法なら当月投入の数量から正常減損の数量を引いた数量で当月製造費用を割って単価をだす。加工費の配分も同じ(正常減損の数量を無視(0)とすれば結果は同じ)
Q:度外視法で、定点発生の場合は正常減損費は( )に負担させ、加工費の進捗度は( )%とみなす。
A:完成品と月末仕掛品の両方、50%
Q:非度外視法の正常減損費は定点発生の場合は( )、平均的は発生の場合は( )で負担する
A:減損発生点と月末仕掛品の加工進捗度を比較して決定、月末仕掛品と完成品の両方
Q:非度外視法の正常減損費の按分基準は定点発生の場合は( )、平均的は発生の場合は( )
A:数量、加工費の完成品換算量
ただし、定点発生は数量で按分しますが、先入先出法で「正常減損は当月投入から発生」とある場合は、完成品数量から月初仕掛品完成分を除いて按分します。
Q:連産品における副産品はその原価を( )、( )を主産物の原価の計算上控除する。
A:計算することなく、評価額
Q:先入先出法で正常減損と異常減損が同月に発生したケースで、異常減損には正常減損費を負担させない 場合、次の場合の材料費の当月投入量はいくらか?
月初100、完成2,000、正常減損200、異常減損30、月末400
A:2300 =2000+400-100、正常減損、異常減損は計算にいれずに貸借差額から計算。ちなみに、当月投入金額をこの数量で割ったものが当月単価となる。
標準原価計算
Q:シングル・プランは仕掛品勘定へ( )原価で振替。(減価差異は( )勘定などで発生)、パーシャル・プランは仕掛品勘定へ( )発生額で振替。(減価差異は( )勘定などで発生)
A:標準,材料,実際,仕掛品
Q:修正パーシャル・プランは仕掛品勘定への直接材料費と直接労務費は( )単価×( )量、製造間接費は( )で振替
A:標準,実際消費,実際発生額
Q:標準原価カードを作る際の計算は仕損費 = (正常仕損品原価 - ( ))x正常仕損率。また、途中で減損が発生する場合は減損の加工費分(直接労務費と製造間接費)は( )
を考慮して計算する。
A:仕損品評価額、加工費進捗度
その他
Q:1個あたりの年間保管費の計算時、材料購入原価、減価償却費、倉庫の電気代の基本料金は、1回あたりの発注量によって変化しないため、( )原価
A:無関連
Q:経済的発注量を求めるとき、年間発注費=年間保管費となる1回あたり発注量を求める。その際、年間発注費 = 1回あたり発注費 ×( )/1回あたり発注量(X)、年間保管費 = 1個あたり保管費 ×1回あたり発注量(X)/2(・・・平均在庫量)が等しくなる形で計算する。
A:材料の年間予定総消費量